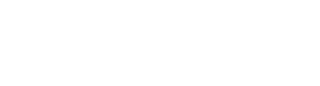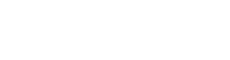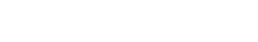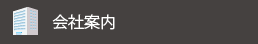【Vol.2】東京多摩相続診断士会に出席してきました。
先日、サウナに行った時、隣でこんな話をしている方がいました。
A:「やっと兄貴の49日も終わってほっとしたよ。」
B:「そりゃあ~大変だったね。」
A:「ホント一人暮らしだったから、病院や葬式とか費用も大変でさあ。」
B:「相続とかどうなるんだい?」
A:「それが、疎遠になっている子供がいるらしいんだけど、何処にいるのかわからないんだよね。」
B:「そりゃあ~大変だ。」
A:「でも、遺留分があるから、心配はしてないけどね・・・・」
「????確か兄弟の相続で遺留分はないはずじゃ?
相続は誰にでも関わりがあるけど、意外とわからない事が多いよなぁ」
そんな事を考えているタイミングに月1回出席している相続診断士会のセミナーで遺留分の講義がありました。
東京多摩相続診断士会 セミナー
11月11日(月)19時~21時 立川にて
テーマは「相続法改正を踏まえた遺留分の実務」
今回、約40年ぶりの相続法大改正となる中で、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に見直される事になります。
と言っても、ピンと来ないかもしれませんが、簡単に言うと、
「遺留分を侵害しているんだから、そんな遺言は無効だ!」としていたことが、「遺言は有効のまま、侵害している遺留分は金銭で解決する」、すなわち「遺留分権利者の権利の金銭債権化」いうことになります。
ちなみに「遺留分権利者」は以下の通りです。
・兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)
・胎児(生きて生まれたら、子としての遺留分を有する)
・代襲相続人
ということで、サウナにいたAさんは遺留分権利者ではないのです。
今回のセミナーでは相続法改正の背景から遺留分侵害額の算定方法まで、事例を交えながら詳しく弁護士の講師の方に教えて頂きました。
しかし、複雑な内容のため、講義終了後、脳みそがパニックになってる自分に自己嫌悪でした。
当社がお手伝いする不動産売却で相続関係が益々増加しており、民法改正に伴い様々な知識を習得する事がお客様のお役に立てる事になります。これからも積極的に情報収集して、皆様にフィードバックできればと考えております。
まずは相続が争族にならないように、親族と相続について、正月にでも話してみようと思います。
追伸:今回のセミナー内容でお伝え出来なかった事は近々に整理し投稿したいと思います。
池田